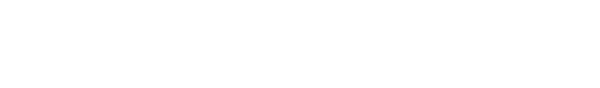前回、スポーツ庁の「生活習慣等に関わる調査」結果から、子どもたちの健康のためには、スクリーンに親しむ時間の自己管理がいかに重要であるかをお伝えしました。
今回は、それに関連して保護者の皆さんにご理解いただきたい内容です。
先日、スマホが身体におよぼす影響などを研究されている浜松学院大学の今井昌彦副学長のお話を聞く機会がありました。
先生曰く、昔は小学生が将来なりたい職業はサッカー選手やパティシエ・お菓子屋さんが上位を占めていましたが、今やIT企業の社長、ゲームクリエーター、ユーチューバーなどが上位にランクイン。
デジタルが遊びから生活の一部になっています。
講演の中で先生が興味深い本をご紹介くださりました。
世界的ベストセラー作家でスウェーデンの精神科医であるアンデシュ・ハンセンの著書「スマホ脳」です。
著書の中で、スマホなどの影響を以下のとおり解説しています。一部をご紹介すると、
- わたしたちは1日平均2,600回スマホを触り、10分に1回手に取っている。
- 脳内の伝達物質/ドーパミンは新しい情報を欲しがる特性があり、SNSはそれを巧みに利用し、開発されている。だから、人間はスマホ依存症に。
- 世界的IT企業の創始者は、わが子にスマホなどのデジタル機器を使う時間を制限。
- 最新のニュース、友達からの誘いなど、様々な情報を提供してくれるスマホを傍らに置くだけで、学習効果、記憶力、集中力が低下。
これらは悪い影響の例示ですが、いまやスマホやインターネットの便利さは認めざるを得ませんし、私たちの生活に欠くことができない道具です。
ならば、スマホなどのデジタルな道具を賢く使うため、まずは保護者の皆さんがメリット、デメリットを正しく理解し、子どもたちに正しい知識とルールを教えていきましょう。
その一つが、子どもたちがスクリーンタイムを「いかに自己管理できるか」です。
保護者の皆さんには、本の巻末「デジタル時代のアドバイス」の一例をご紹介します。
- 集中力が必要な作業をするときは、スマホを別の部屋に置く
- 寝る時は脳を休ませるために、スマホを別の部屋に置く
- 目覚まし時計を復活させるなど、スマホでなくても良い機能はスマホを代用しない
- 人と会っている時、あなたがスマホを取り出せば、周囲にも伝染する
 学習以外での「スクリーンタイム」を自己管理できる子どもに! パート1
学習以外での「スクリーンタイム」を自己管理できる子どもに! パート1